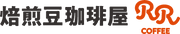土曜日
文:Soichiro Kano
都会の喧噪の中、僕たちはその喧噪の一部になりながら毎日を消化する。そもそも、一週間のうち五日も身を粉にしないといけないなんて、割に合わないじゃないか。そう愚痴を零しながら、珈琲を淹れる。今日はいつもより所作が遅い。遅くていい日なのだ。
珈琲を一口。淹れたては熱い。鼻腔をくすぐる苦く香ばしい香りが部屋に広がる。僕は日のあたる場所に椅子を用意して、本を一冊、まだ新しい本棚から取り出した。
一ページめくる。分からない単語がたくさん出てくる。書店で適当に選んだこの本は手ごわそうだ。気が向いたらば意味を調べたり、意味を推し量ったり、自己流で文字列の波を乗りこなしていく。まだまだ波乗りまでの道のりはまだまだ長い。
珈琲を一口。人肌ぐらいの温さだ。これぐらいの温さなら、飲み切ってしまいたいところだが、今日はなんだか少しずつ飲みたい気分だ。身体が少しずつこの空間に溶解していく。
一ページめくる。何となく全体が読めてくる。本はまるで傷薬だ。自分が痛いと思っている場所に響く。きっとこの本も、十年後読み返したときには違う傷に響くに違いない。そう思いながら、僕は喧噪で浴びた傷を癒す。
珈琲を一口。少し冷たくなってしまった。口の中で温められ珈琲の香りが広がる。もう一杯入れようか。今日はこれぐらいにしようか。贅沢な悩みだ。
一ページめくる。目が文字を滑っていく。久しぶりの早起きだったからか、すごく眠い気がする。僕は珈琲が眠気覚ましになるなんて都市伝説だと思う。陽の光と本と珈琲は、どんな薬よりも身体に良いに違いない。
ああ、なんて贅沢な日だ。こんなに自分を満たせる日があっていいのだろうか。僕たちは毎日時間を管理しているつもりでも、時間に管理されているだけなんじゃないか。自分を自分たらしめる時間こそ、最高な贅沢ではないのか。
尊大な声を心の奥で上げながら、手に取った本を机に置いて、僕はひなたぼっこを始めた。