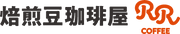エスプレッソのきっかけ
文:蓑毛宏明
エスプレッソを飲むようになったのは、22歳だった。はじめて国境を超えたのも、22歳の時。2ヶ月間の短期留学で、フランスのリヨンだった。8月15日夕方、お煎餅とお味噌汁で嵩んだ巨大なスーツケースと小さいスーツケースとリュックサックに連れられ、エスプレッソの国に降り立った。受け入れ先のSimonが教えてくれた電車に乗って、予定通りの駅で降り、このバスに乗ればホテルに到着だ。バスを待つこと30分、不安になってきた。待つこと1時間、少し暗くなってきた。一台もバスが通らないなんてことはあるのか。カップルは道を教えてくれるはずだという不確かな思い込みから、通りがかりのアジア人夫婦に助けを求めた。
「バスがこないんだけど」
「今日は祝日だよ」
祝日にバスが走らないことがあたかも当たり前のような発言である。しかし、それが当たり前なのである。
「ここからまた中央駅まで電車に乗って、タクシーに乗るしかない。」
「わかった。でも券売機で切符を買う小銭がない」
「じゃあ貸してあげるよ。」
ちゃりん。人生初の借金を背負った青年は、またお煎餅とお味噌汁で嵩んだ巨大なスーツケースと小さいスーツケースとリュックサックに連れられ、ホテルに着いた。日付も変わりかけていた。翌日、予定よりも3時間遅刻して「Bon jour」とホテルに迎えに来たのは、Simonだった。私の所属したコンクリートの研究室には毎日コーヒータイムがあった。お昼休みの「後」に1時間、エスプレッソ片手にサッカーや政治やパーティの議論をするのが、至福の時だそうだ。初めてコーヒータイムに参加した彼は、飲んだこともないエスプレッソを片手に、昨夜の未曽有の大冒険のエピソードを披露した。Simonは軽く笑っていた。エスプレッソの感想は「苦くて少ない」という無機質なものだった。しかし、それまでコーヒーすら飲まなかった青年が、たった3ヶ月の異文化体験からの帰国後に、当たり前のような顔をしてカフェでエスプレッソを注文するのだから、たいした柔軟性である。